
【Grip the Rein 合同会社】裁縫の概念を覆すオリジナル刺繍で市場を拓く【港区のベンチャー企業】
港区でスタートアップ事業の支援を行っている『港区立産業振興センター』に集う方々にお話を聞きながら、区内のベンチャー企業を紹介していく企画も4回目。今回、産業振興センターのご担当者様にご紹介いただいたのは、Grip the Rein合同会社の大井想太さん。
「刺繍を使った商品を開発している方」とざっくりした情報しか得られず、普通のアパレルブランドだったら、あまり『いざまち』らしくない記事になりそうだなあと取材前は不安でしたが、いざ話を伺ってみるとびっくり。
とてつもないことをやっている、“職人”だったのです。
業務用刺繍ミシンとの出会いが事業化のきっかけ
Grip the Rein 合同会社は登記自体は2021年9月ですが、本格的に事業がスタートしたのは2023年12月というスタートアップ企業でした。

大井さんにお話を伺わせていただいたのは、産業振興センター内の『ビジネスサポートファクトリー』
「もともと、刺繍を使ったものづくりが好きで、以前から産業振興センターを利用させてもらっていたんですよ。ただ、あくまで趣味の延長線上でやっていて、副業というレベルです。本業はサラリーマンでした」
大井さんは、元々一般企業の経理マン。毎日決められた時間で働く傍ら、趣味で手縫いの刺繍を続けていたのだそうです。
「刺繍って、どのくらい時間がかかるか知っていますか?例えば、3cm×3cmのワッペン1つを作るのに、大体8時間くらいかかるんです。こんなに時間がかかっていたら、とてもじゃないですが商売になんてならないでしょ。だから刺繍は趣味で留めておこうと思っていました」
刺繍という作業が、大変地道で今期のいる作業だということは、知識として知ってはいましたが、そんなに時間がかかるとはまるで知りませんでした。たしかに、お一人で、仕事としてやるとなるとものすごく低い時給換算となりそうです。
ところが、そんな大井さんに、とある出会いが訪れます。
「2020年に閉鎖してしまったのですけれど、溜池山王にTechShopという大きなDIY工房がありました。そこで、業務用の刺繍ミシンに初めて触れたんです。それまで8時間かけていた刺繍作業が、業務用のミシンだと数分で作ることができました。衝撃でした。これさえあれば、一人でも生産効率を上げられると、うっすら事業化を考えるようになったんです」
大井さんは、刺繍だけでなくレザークラフトもされています。自作の皮製品が、商用として市場に並べても遜色ないレベルにまでなってきたこともあり、副業ではなく専業として開業に踏み出すことを決めたのでした。
ところで、聞き馴染みのない“業務用の刺繍ミシン”というのは、どのようなものなのでしょうか。
「この機械は糸を10色までセッティングすることができます。あらかじめ、パソコンのソフトで設定した色とデザインをミシンにインストールすれば、そのデザイン通りに、自動で刺繍を行ってくれるのです。縫う工程は機械が行うので、私は今、専らデザインを起こしていますね。刺繍用ミシンのデザインは、専用のソフトウェアで作成しなければなりません。使用者が少ないため情報が少ないのですが、持ち前の探求心をもって研究を続けた結果、他社では真似できない刺繍データを作成する技術を身に付けました」
大井さんが得意とするのが、刺繍によるグラデーション加工です。大井さんの作品は、一見浮き出たり、蛍光色の糸を使っていたりするように見えますが、すべて、糸の色を組み合わせることで立体的に見えるように細工を施しただけなのだそうです。
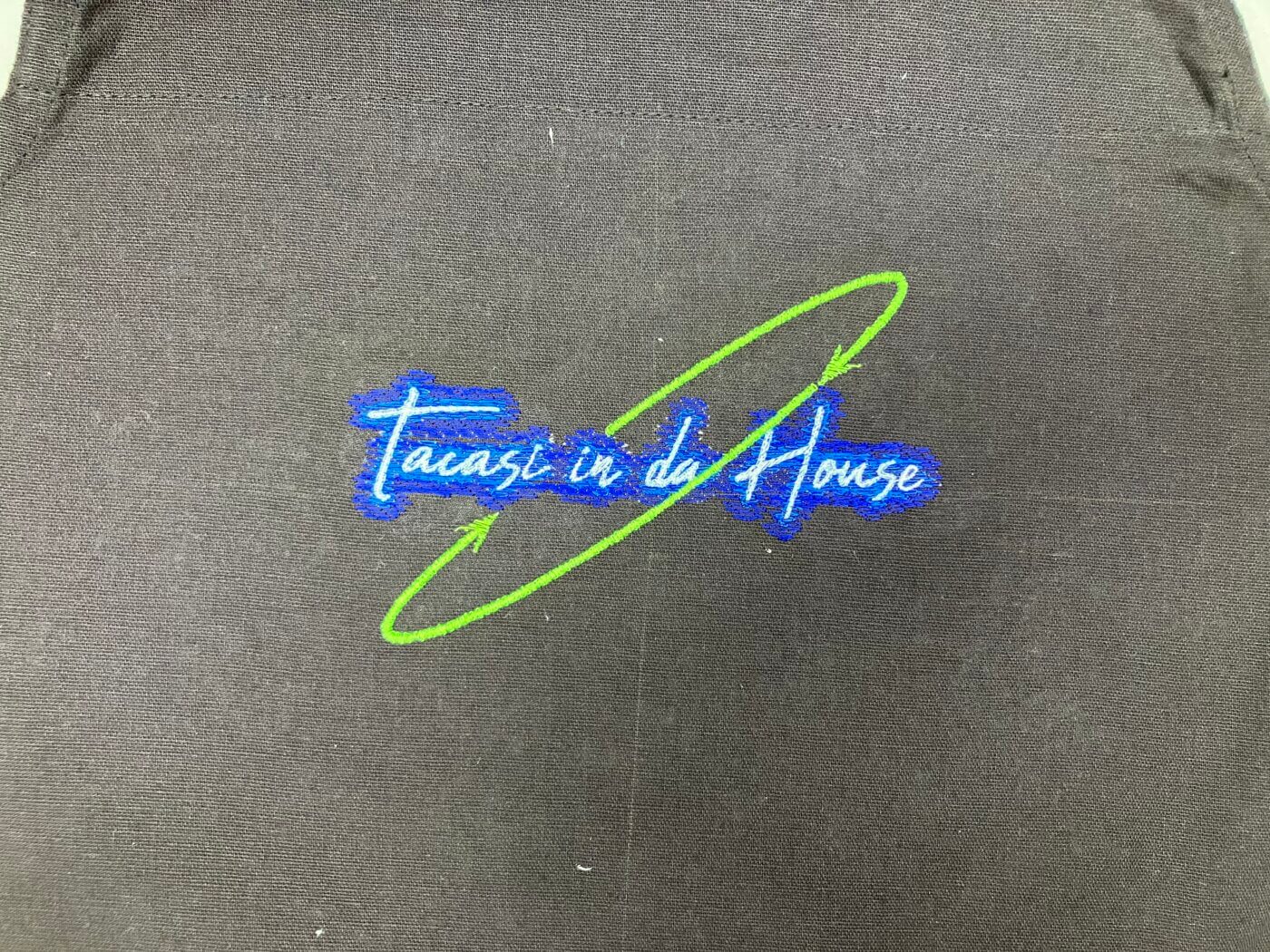
刺繍糸の膨らみにグラデーションが重なることでより立体感を増した仕上がりとなる
「夜の町の中で、ネオンサイン管って目立つじゃないですか。ヒントにしたのはあれです。刺繍の魅力は立体感なのですが、そこにさらに光って見えるような工夫を施したらどうなるだろうと。この刺繍の縁をよく見てください。よく見ると、外枠と内側と色が違う色のの糸を使っているでしょう?こうすることで、人間の目をだまして光っているように見せているんです。グラデーションにこだわり過ぎてしまって、この間は刺繍ソフトウェアメーカーに機能の強化リクエストを出してしまいました。幸い、その機能は次のアップデートで追加されることになりました」
この光って見えるようにデザインを施す技術は、大井さんが独自に生み出したため、他社にはなかなか真似できないとのことです。
業務用の刺繍ミシンが可能とした全く新しい刺繍製品
さらに、Grip the Rein合同会社にはもう1つ、独自の技術があります。なんと大井さん、紙へ刺繍を施すという技術を開発されたのです。

サンプルとして見せて頂いた刺繍を施した紙袋と紙箱
「刺繍は模様を施す素材に一定間隔で針を通さなければなりません。普通の柔らかい紙に対してそのようなことをすると当然破れてしまいますし、多少強い紙を使ったとしても、まるで切り取り線かのようなミシン目になってしまいまね。ですが、私は紙の裏に1枚補強となる別の紙を接着すれば、不可能ではないと考えました。裏地となる紙の素材選定に試行錯誤を繰り重ねた結果、紙を破らずに刺繍を施せるようになったんです」
凄い技術です!ちなみに、最初にこの話を聞いた時、ミシンの側に加工が必要かと思ったのですが、大井さんによるとミシンのほうには何も加工は必要ないとのことです。それならば、特別な改修コストもかからないということで導入の障壁も低そうです。もっとも、話を聞いただけでは、紙に施された刺繍が利用されるシーンがあまり浮かびません。正直にそうお伝えすると、大井さんは現在考えているビジネスビジョンを語ってくださいました。
「例えば刺繍でロゴや名称を施した紙袋や、製品の包装箱、高級感のある酒瓶ラベルなどを考えています。刺繍の施された紙はこれまでにないデザイン性と機能性を持つ製品です。だから、ブランドがしっかりしている商品や、お店に向けてなら勝負になると思っています。もちろん、実用化・量産化に繋ぐことが出来なければ技術だけあっても意味がありません。現在、紙箱メーカーと連携しながらサンプル作成を行っており、量産体制を構築するための生産ラインも設計中です」
なるほど、百貨店や宝飾品などの紙箱に刺繍が施されていたら、受け取った方のインパクトは抜群ですし、大切にとっておこうという気になりますね。
経営的な目線と職人的な目線のハイブリッドでビジネスを仕掛ける
Grip the Rein合同会社は、現在、洋服などに光る刺繍を施したアイテムを販売する傍らで、紙への刺繍を量産するための準備を行っていらっしゃいます。大井さんは、まず何よりも取引先を見つけることが課題と語ります。
「例えば刺繍で社名の入った紙袋でしたら、全国の全ての法人を顧客できる可能性を秘めた商品です。ですが、いくら機械を使って半自動で生産する刺繍だとはいえ、通常の印刷と比較するとはるかに高コストとなってしまいます。だから現実的には、顧客は限定されるはずです。だいたいどの程度の事業規模のお客様を探すべきか、こういったときにすぐに頭の中で算盤をはじけるのは、経理職に従事していた経験があってよかったなと思っています。数字に強くて物が作れる“一人製造業”の面目躍如ですね」
若くて技術のあるクリエイターさんが、商品は良いのに売り上げや仕入れの予測を見誤り経営が回らなくなるということは、残念ながらよく聞きます。Grip the Rein合同会社に関しては、そこはあまり心配しないでよさそうです。とはいえ、顧客開拓となると今度は営業という分野の力も必要となりますので、これからが踏ん張り時なのでしょう。
さらに大井さんは課題と感じている点について教えてくれました。

サンプル品を1つ1つ手に取りながら、刺繍の魅力を語る大井さん
「ECサイトとSNSの運用は本当に難しいですね……。今は自分でやっているのですが、やはりネット関係のプロが運営していないので見た目が非常に素人感が出てしまっています。特に、私が撮影した写真だとスマホやPCのモニタ上で刺繍の立体感が伝わらないことは、完全に盲点でした。紙に刺繍を施すプロジェクトは様々な商品に応用できると考えていますので、まずはこちらを推進し収益を確保。金銭的に余裕ができたらすぐにでも、サイトの見直しと改修に取り掛かりたいです」
Grip the Rein合同会社は、大井さんが専業にされる前から、港区産業振興センターを拠点として活動されていたそうですが、現在は、登記のみ港区産業振興センターで行い、業務用の刺繍ミシンを置いた自前の工房を用意されたそうです。
「港区産業振興センターを知ったのは、先のTechShopの閉館後のことです。当時、TechShopにいたメンバーから港区に新しいDIY施設ができたという情報を貰い、業務用の刺繍ミシンを使わせてもらいに会員登録をしました。そこからは、あれよあれよ、という感じでしたね」
実際に、産業振興センターを使用してみてどう感じたのでしょう。
「私の現在の工房も港区に籍を置いています。産業振興センターさんには施設の利用以外にも、港区の色々な支援制度のご紹介などでお世話になっており非常に感謝しております。やはり、施設の利用と行政の支援設備とか同じ建物の中にあるというのは大変助かりますね」
なるほど、では、ちょっと意地悪な質問を。実際に利用してみた目線から、こういったケアが欲しいといったご要望はないのでしょうか?すると、大井さんは、あえて言うならということでこのような話をしてくださいました。
「マッチングという言葉は安易なイメージで好きではないのですが、企業同士を繋ぐ結節点(ハブ)としての制度、もしくは施設の機能があれば嬉しいです。昔のバンドメンバー募集の掲示板のイメージですが、利用している企業同士で“弊社〇〇できます”“△△できる会社を探しています”“一緒にサンプル作りたいです”といった情報を物理的な掲示板や、オンラインサイトで情報共有出来たら面白いかもしれません」
確かに、Grip the Rein合同会社を筆頭に、斬新な技術を持った起業家の方がこれだけ集まっているのですから、強引にでもシナジーを生み出すための仕掛けがあると、さらに面白くなりそうです。最後に、大井さんに今後の事業の展望について語っていただきました。
「まず、紙に刺繍については牛乳パックのような箱状の製品に対して、縁部分を跨いで刺繍を施す技術を開発中です。結構、完成に近いところまで来ていると思います。この技術が完成すれば、例えば刺繍の絵がぐるりと四面跨いで繋がって描かれていても図柄として成立させることができるんですね。外国人向けに和風の図柄を刺繍したペン立てなんかをお土産として販売してみたり、本の装丁を刺繍で施したりしてみても面白いかもしれませんね。また、今は刺繍関連の業務で手一杯ですが、なんとかこれを軌道にのせられたら、次は革製品の取り扱いを視野に入れています。型紙も自分で起こすことが出来るまで腕を磨きましたので、オリジナルレザーアイテムを販売して二軸で展開していきたいですね」

紙の刺繍の将来性を語る姿は、まさにこれから勝負に出ようとされるビジネスマンでした
たった一人で生み出した唯一無二の技術を武器に、これまで存在しなかったマーケットの開拓を始めるGrip the Rein合同会社。もしかしたら、お土産でもらった紙袋や紙箱に、大井さんの刺繍が施されている時代が来るかもしれませんね。




